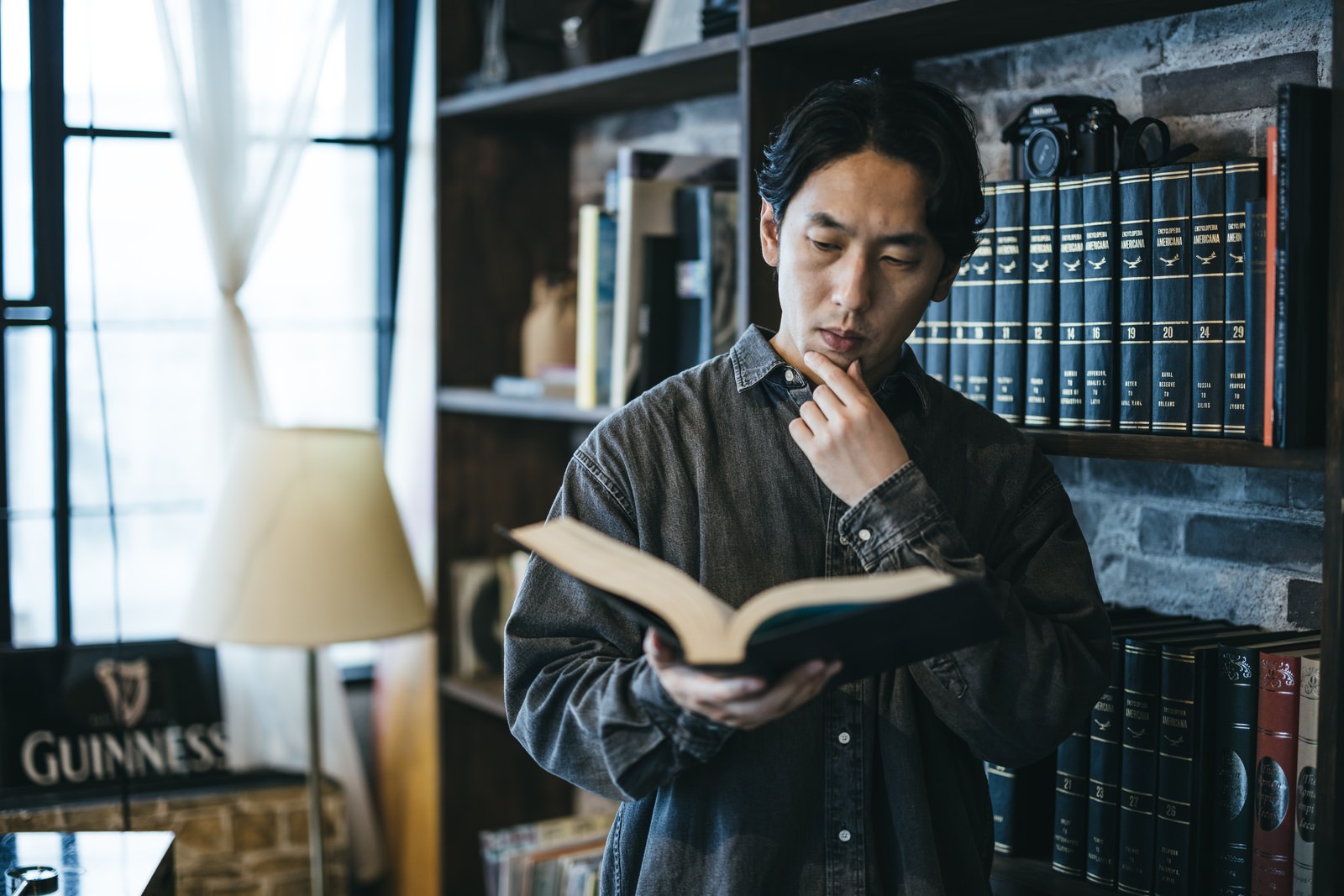最近、本の読み方を少し変えてから、またちょっと本を断捨離できた。
以前の記事(前から気になっていた本の断捨離をしつつ読書のやり方を変える)でも書いたけど、斜め読みをするようにしている。
もちろん、普通に読みたい本などは最初から最後までじっくり読んだりするけど、「少し気になるな」程度で買ってみた本は、斜め読みでザッと全体像を掴んだり、必要な箇所だけ拾い読みをして読了。
斜め読み、拾い読み、この2つをするだけで、割とサクサク読めるようになってきた。
本を読んでいて思うことだけど、タイトルに惹かれて、目次もチェックして、中身も少し見て、それで買ったとしても、タイトルや目次とはズレた内容が書いてある事がある。
色んなブログなどを見ていてもそういう事が多々あるが、本でもある。
その場合は、もうその本は読まないようにしている。
だってその先を読んでも、ズレている可能性があるから。
そうやって自分なりの基準というか、その本に対して「求めているもの」だけ読んだり、読んだけど求めているものが無かった場合、もう見ない。
自分は小説をほとんど読まず、読むとしてもビジネス書や、何かその時気になって勉強したい分野の本などがメイン。
だからこそ、斜め読みや拾い読みで十分とも言える。
そうやってサクサク見ていって、必要な箇所だけ読んだり、期待した内容と違ったり、分別していったら2日で17冊ほど断捨離できた。
捨てるのはもったいないから、もちろん古本屋に売りに行ったけど。
自分は本の中に確固とした「答え」があるように思っていた。
でも最近はそうじゃなく、「参考」程度に思うようになっている。
考えてみれば、本を読んだからといって、自分が今すぐ同じことが出来るわけじゃない。
知る事はできても、その本を書いた作者とは、能力、才能、環境、人脈、時代、それら以外にも様々な要素が全く違っている。
なのに、本の内容をそのままやって同じように出来る。と考えること自体、凄く傲慢で安易なんじゃないかと。
そう思うようになったからこそ、サクサク見ていって、必要な部分だけ参考にして、あとは手放す。ということに抵抗がなくなってきたんだろう。
こういう本の読み方をするようになってから、読書が楽になってきた。
今までは最初から最後までとりあえず読む、みたいに考えていたから、そもそも本を読み始める前の心理的ハードルが高かったんだ。
でも読みたい気持ちはあるから、気になった本を買う。
そして積読が増えていく。という流れだった。
買う本も厳選するようになった。
気になる本があってもすぐには買わず、ネット書店で検索して目次を見たり、サンプルが見れたら少し読んでみたり、図書館に在庫があるか検索してみたり。
最近、気になったけど買うのはどうかな?と思った本が図書館にあったので、それを図書館の本棚の前で立ちながらザッと読んでいった。
で結果、それで満足できた。
自分が知りたい内容の、知りたい箇所を読めたから。
だから気になったからとドンドン本を買うんじゃなく、図書館にあるかまず検索して、立ち読みしてみて、それでもじっくり読みたいなら借りて、借りて読んで本当に自分に必要だと思ったら買う。というのが良いんじゃないかと今は思う。
本の選び方、買い方、読み方に正解はないと思うけど、何となく自分に合う方法が見つかったような気がする。
ま、これもまた変わるかもしれないけど。